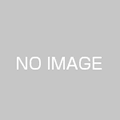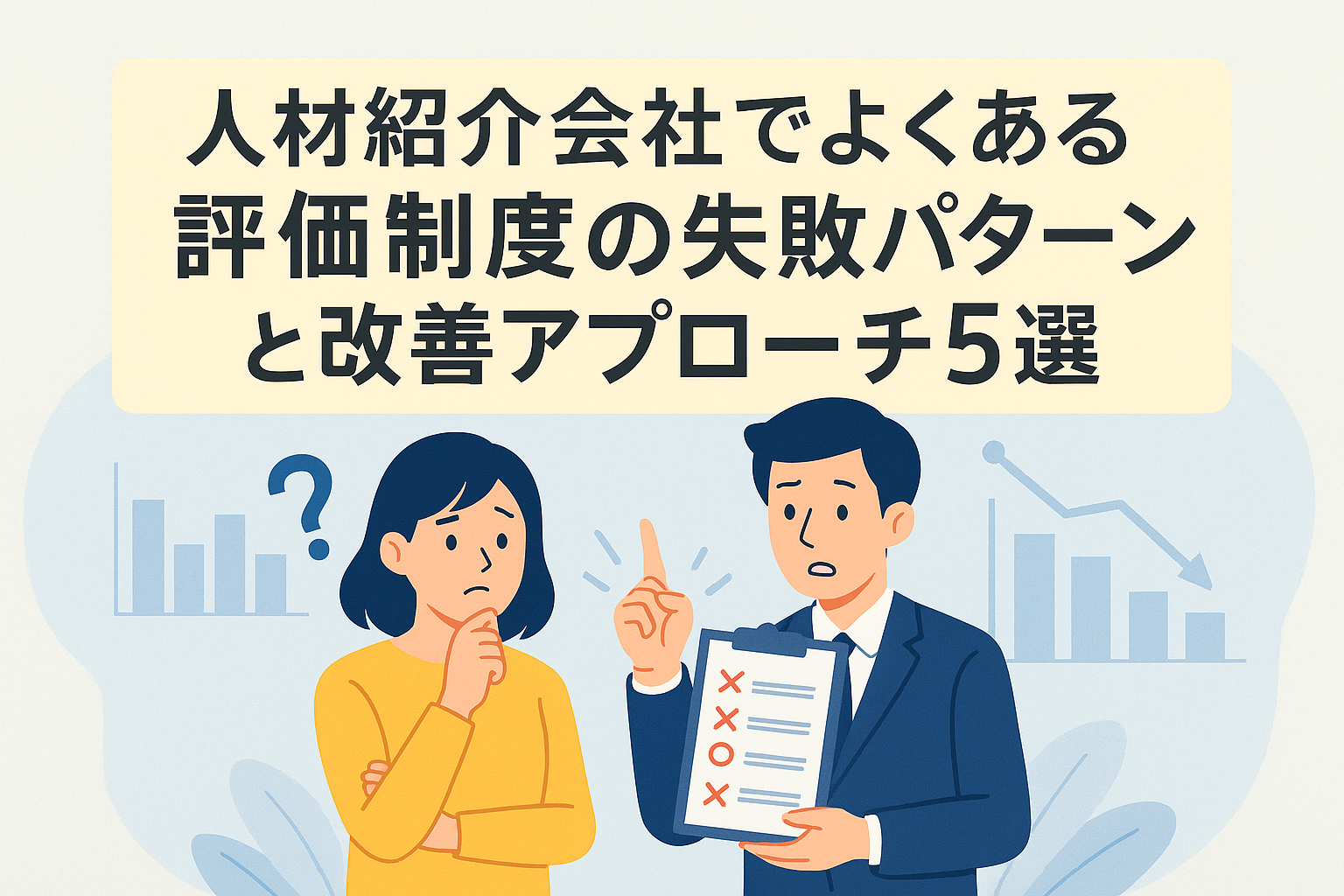
人材紹介会社で働く現場の声として、「成果が出ているのに評価に納得感がない」「頑張っても数字だけで判断される」など、評価制度にまつわる悩みはつきものです。マネージャーも、組織が成長してメンバーが増えてくると、「どう評価すべきか?」という問いに向き合わざるを得ません。
本記事では、人材紹介会社・転職エージェントの評価制度設計でありがちな失敗パターンを5つに整理し、その改善アプローチをご紹介します。組織の透明性を高め、メンバーのモチベーションを引き出す制度設計のヒントとしてご活用ください。
人材紹介会社の評価制度設計でよくある失敗パターン5選
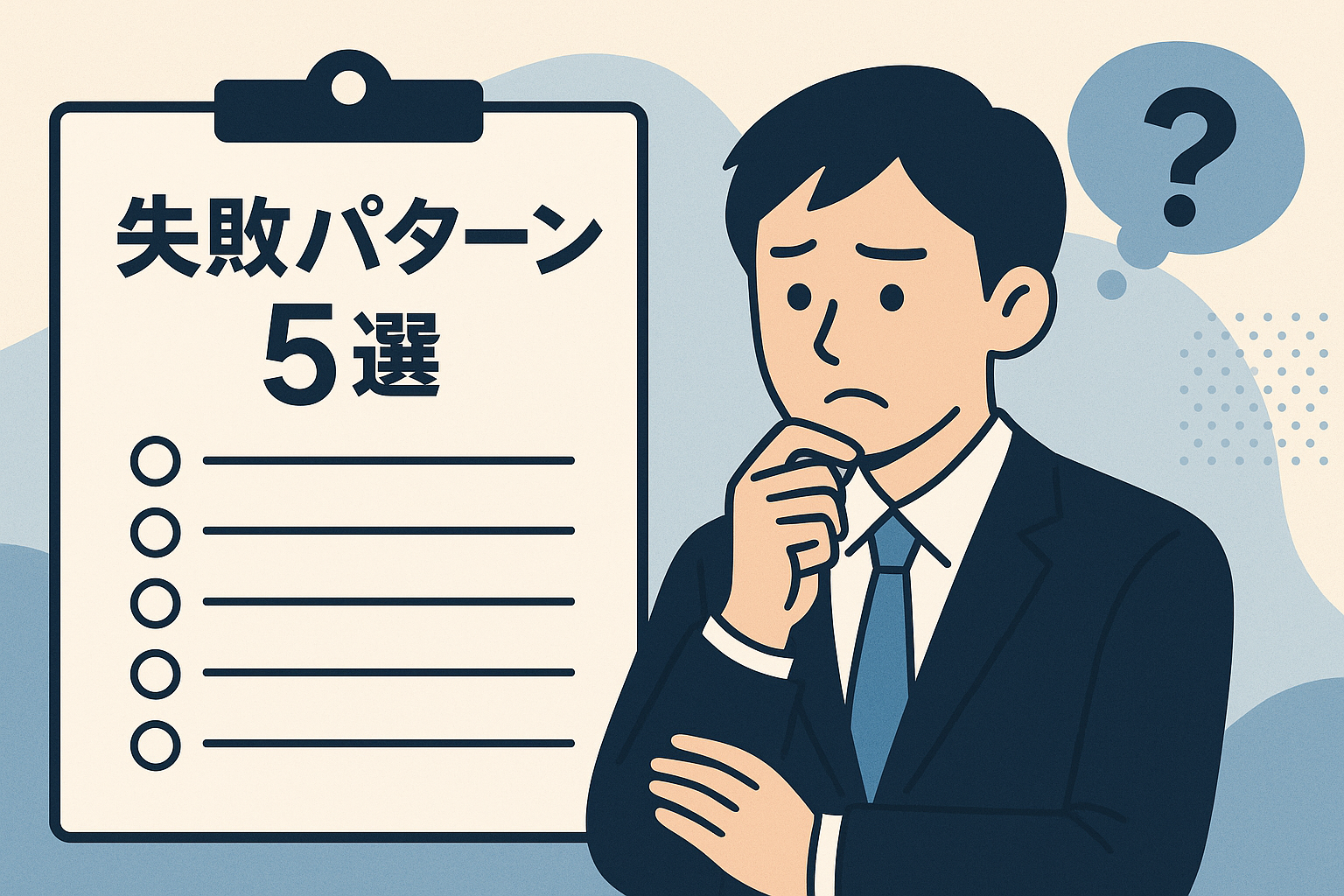
まずは、よくある5つの失敗パターンとその頻度を確認しましょう。
| 失敗パターン | 頻度 |
|---|---|
| ① 成果(売上)評価に偏りすぎている | ★★★★★ |
| ② 面談数や推薦数などKPIが曖昧/不整合 | ★★★★☆ |
| ③ 評価基準が属人化・ブラックボックス化している | ★★★★☆ |
| ④ 活動履歴が残っておらずプロセスが評価できない | ★★★☆☆ |
| ⑤ 評価制度が運用されず形骸化している | ★★★★★ |
それでは、ここからは5つの失敗パターンについて、具体的な事例や背景を詳しく解説していきます。
▼ ① 成果(売上)評価に偏りすぎている
紹介手数料や成約件数などの売上指標だけで評価していると、どうしても短期成果ばかりが重視されがちです。その結果、「とにかく決めればOK」という風潮になり、求職者対応の質や長期的な関係構築が後回しになるケースもあります。目先の決定件数を優先し、本来マッチするとは思っていないような求人を紹介してしまう、なんてことも起きかねません。
▼ ② 面談数や推薦数などKPIが曖昧/不整合
KPI(重要業績評価指標)は、評価制度の基盤となるものです。しかし、たとえば「面談数」「推薦数」「求人提案数」といった指標の定義がチームごとにバラバラだったり、RA(リクルーティングアドバイザー)とCA(キャリアアドバイザー)で同じKPIを使っていたりすると、現場で混乱が生じ、公平な評価ができなくなります。
よくあるのが、「面談数は多いのに推薦に結びつかない」「推薦数は少ないが高い確率で成約している」といったケースで、どちらが正しく評価されるのかが曖昧だと、メンバーも「何を頑張れば評価されるのか」が分からなくなってしまいます。
制度として機能させるには、職種や役割に応じて、明確で一貫性のあるKPIを設定することが不可欠です。
▼ ③ 評価基準が属人化・ブラックボックス化している
「なんとなく印象で決まっている」「上司との関係性で評価が左右される」など、評価プロセスがブラックボックス化しているケースも見られます。評価の透明性が低いと、頑張るモチベーションが削がれやすく、離職リスクも高まります。
特に新卒や若手にとっては、何が評価されるのかが見えないと、育成にも支障をきたします。属人的な判断に頼りすぎる設計は、組織拡大にとっても大きな障壁です。
▼ ④ 活動履歴が残っておらずプロセスが評価できない
求職者との面談内容や企業への推薦履歴など、日々の活動がきちんと記録されていないと、プロセスを正しく評価することができません。その結果、「地道に取り組んでいるのに評価されない」と感じるメンバーが出てきたり、成果(成約数や売上)ばかりが重視される評価になってしまいがちです。
たとえば、面談時に丁寧なヒアリングや求人提案の工夫をしていたり、推薦時に書類添削や面接対策をしていたとしても、記録がなければ評価に反映されません。こうした“見えにくい努力”を適切に評価するには、活動ログを蓄積できる仕組みを整えることが不可欠です。プロセスを可視化することで、より公正で納得感のある評価が実現します。
▼ ⑤ 評価制度が運用されず形骸化している
どれだけ精緻な評価制度を作っても、現場で活用されなければ意味がありません。評価項目が複雑すぎて実際にはチェックされていなかったり、評価会議のときだけ使われる“棚上げ資料”になってしまっていたりと、制度が形だけのものになるケースは少なくありません。
また、「制度はあるけれど、誰も見ていない」「自分の評価にどう関係しているのか分からない」といった状態では、社員の納得感や制度への信頼も得られません。
評価制度は“設計すること”が目的ではなく、“日常的に使われること”が重要です。月次の振り返りや1on1面談など、日々のコミュニケーションの中で制度を活用していくことで、形骸化を防ぎ、実効性のある仕組みとして現場に根付かせることができます。
失敗を防ぐ!人材紹介会社の評価制度設計・5つの改善アプローチ

自社の評価制度の課題を見極めたうえで、以下の対応表を参考に最適な改善策を取り入れましょう。
| 失敗パターン | 有効な改善アプローチ |
|---|---|
| ① 売上評価に偏り | 売上とプロセスの両面評価に切り替える |
| ② KPIが曖昧/不整合 | 職種別・役職別で評価軸を設計する |
| ③ 評価基準がブラックボックス化 | 評価基準のマニュアル化・共有 |
| ④ 活動履歴が残っていない | CRMやSFAで活動記録を自動ログ化 |
| ⑤ 評価制度が形骸化 | 月次振り返りや1on1で制度を運用する |
自社の状況に合わせて、最も必要なアプローチから着手することで、制度の形骸化や不公平感を防ぐことができます。
▼ ①売上評価に偏り → 売上とプロセスの両面評価に切り替える
人材紹介においては、成約件数や売上といった成果指標だけで評価を行うと、短期的な成果を優先するあまり、本来のマッチング品質や求職者対応の丁寧さが損なわれるリスクがあります。そこで、面談実施数や推薦率、書類通過率、初回面談からの期間など、プロセスに関する指標をあわせて評価に取り入れることが重要です。
とくに立ち上げ期のコンサルタントや、目標に届いていない社員に対しては、「行動しているかどうか」が可視化されることで、モチベーションの維持や成長支援にもつながります。成果だけでなく、過程も含めてフェアに評価する仕組みが、組織全体の健全な営業スタンスや長期的なパフォーマンス向上に寄与します。
▼ ② KPIが曖昧/不整合 → 職種別・役職別で評価軸を設計する
RA(リクルーティングアドバイザー)とCA(キャリアアドバイザー)で担当業務や目標が異なり、さらにプレイヤーとマネージャーでは求められる成果の質と範囲も大きく変わります。しかし、それらを十分に加味せずに一律のKPIで評価を行うと、現場での納得感を得にくく、不公平感やモチベーション低下を招く恐れがあります。
たとえば、CAには「面談満足度」や「推薦率」、RAには「商談創出数」や「決定単価」など、それぞれの業務成果や価値貢献を可視化できる指標を設計する必要があります。さらに、マネージャーには「育成力」や「チーム目標の達成度」といった組織成果への貢献度を加味することで、役割に応じた妥当な評価が可能になります。職種・役職ごとに明確で整合性の取れたKPIを設計することで、メンバー個々が自身の成果を正しく理解し、納得感のある評価・成長サイクルを実現できます。
▶ KPIを現場に浸透させるには?人材紹介会社の仕組みづくりと運用のコツを見る
▼ ④ 評価基準がブラックボックス化 → 評価基準のマニュアル化・共有
評価制度における最大の不満要因の一つが、「なぜその評価になったのか分からない」というブラックボックス化です。評価指標やその算出方法、評価の進め方を明文化し、マニュアルとして全社員に共有することで、制度への透明性と信頼性を高めることができます。
あわせて、評価会議の進行方法や判断基準もガイドライン化することで、評価者ごとの解釈のブレを抑え、より公平な評価が可能になります。さらに、評価者向けの研修やロールプレイを取り入れることで、評価スキルを標準化し、現場に浸透させていくことが重要です。こうした取り組みによって、社員一人ひとりが評価制度を理解し、自らの行動と成長を結びつけやすくなります。
▼ ③ 活動履歴が残っていない → CRMやSFAで活動記録を自動ログ化
面談実施・求人提案・日程調整・企業フォローなどの活動履歴は、評価制度設計やマネジメントにおいて非常に重要なデータです。しかし、これらを人力で記録・管理するには大きな手間がかかり、記録漏れや属人化による抜け漏れが発生しやすくなります。
そのため、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)を導入し、面談・推薦・商談などの主要な活動を自動または半自動でログ化できる仕組みを整えることが重要です。活動ログを正確かつ網羅的に蓄積することで、どのような行動が成果に結びついているのかといった因果関係を分析でき、評価指標の精度向上にもつながります。
結果として、主観や印象に左右されない公正な評価運用が可能になり、現場の納得感や改善サイクルの質も向上します。データに基づく評価は、育成や制度設計の信頼性を支える基盤ともなります。
▼ ⑤ 評価制度が運用されず形骸化 → 月次振り返りや1on1で制度を運用する
どれほど優れた評価制度を設計しても、実際に現場で継続的に使われなければ意味を持ちません。制度が「評価のタイミングだけのもの」となってしまうと、形骸化し、社員からの信頼を失うリスクがあります。
そこで重要なのが、制度を日常的なコミュニケーションに組み込むことです。たとえば、月次のKPIレビューや1on1面談を通じて、上司と部下が評価指標に基づいた振り返りや目標設定を行うことで、制度の定着と活用が進みます。
また、評価時には単なる数字だけでなく、行動の背景やその意図まで丁寧に確認・共有することが、納得度の高い評価につながります。制度は“紙の上”ではなく、“現場で活きる”形で運用されてこそ、個人の成長支援や組織成果の最大化に貢献するものとなります。
評価制度の設計・運用におけるCRMの活用メリット

評価制度設計においては、「行動の可視化」と「集計の効率化」が鍵を握ります。そのための有効な手段が、CRMの活用です。
CRMを使えば、面談や推薦などの行動履歴を自動的に蓄積でき、評価の根拠となるデータが整います。月次レポートの作成や1on1の振り返りにも活用可能です。
たとえば、キャリアバンククラウドのような人材紹介会社専用CRMなら、
- 求人推薦の通数
- 面談回数
- 決定率
などの重要指標を一元管理でき、制度設計・運用の精度が格段に向上します。複数メンバーの評価対象データも一元化できるため、評価者の業務負荷を軽減する効果も期待できます。
まとめ:制度は「仕組み」と「ツール」で回す
評価制度は、メンバーの行動を方向づけ、組織の成果を最大化するための重要な仕組みです。しかし、「制度設計」にこだわりすぎて、運用が追いつかないまま形骸化するケースも少なくありません。
評価制度を継続的に回していくには、誰でも理解できて、納得しやすく、運用しやすい「仕組み化」と、日々の行動をデータで支える「ツール活用」の両輪が欠かせません。
キャリアバンククラウドでは、評価設計・KPI設計に役立つ資料を無料配布中です。ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
\人材紹介会社向けCRMなら「キャリアバンククラウド」/
- タグ検索で求人・求職者をスピーディに管理
- 初期費用無料&月4,980円~使える!
- 営業・CA間の情報共有もスムーズ
- 小規模チームでもすぐ使える直感UI
📩 無料資料ダウンロードはこちら
(1分で完了/導入相談もOK)